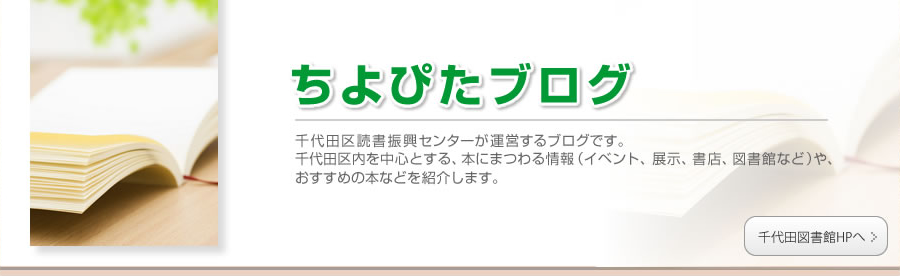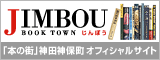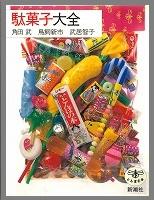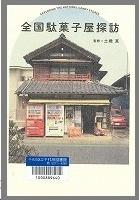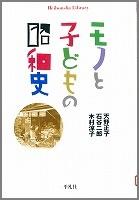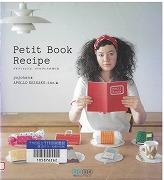カテゴリー
アーカイブ
最近の記事
千代田図書館では、本を通じた交流の場として「本と出会う 読書サロン」を年2期(6月~9月、12月~翌年3月)、「読書の会」主催で行っています。1冊の本について語りあう読書会とは違い、テーマに沿った本を各メンバーが選んで持ち寄り紹介しあうのがこの会の特徴です。
今回は、12月から始まる第19期のメンバー募集を兼ねたオープニングイベントとして開催した講演会「子どもの本の翻訳って?」の様子をご紹介します。
ゲストは、翻訳家のさくまゆみこさん。
これまで200冊以上の絵本・児童書などの翻訳を手がけてきたさくまさんに、まずは子どもの本を翻訳するということについてお話しいただきました。
一般に翻訳というと外国語を日本語に訳すパターンと、日本語を外国語に訳すパターンがありますが、さくまさんの主なお仕事は外国語(おもに英語)から日本語への翻訳。
外国語のスキルが必須なのはもちろんですが、原文で書かれていることをちゃんとした文章で子どもたちにおもしろく伝えるためには、日本語がとても重要になります。
翻訳に至るまでの流れから実際の作業についてお話いただく中で感じたのは、さくまさんは本との出会いをとても大切にしているということ。
「翻訳すべき本は、子どもにとって窓になる本であるように」
本を開くことが、日常と違うすばらしい景色を見られるものであってほしい。もしも嫌なことがあれば、本がそこから逃れられる場所であってほしい。窓を開けるのは子どもだが、その窓を用意してあげるのが大人の役目であるとおっしゃいました。
また、翻訳の作業に要する長い時間の中で、その本に書かれた作者の思いを追体験することになるといいます。『路上のストライカー』(マイケル・ウィリアムズ/作、さくま ゆみこ/訳、岩波書店)や『ローザ』(ニッキ・ジョヴァンニ/作、ブライアン・コリアー/絵、さくま ゆみこ/訳、光村教育図書 )は、国や文化の違いはあっても日本の子どもたちの心にきっと届くものがあるはずだと感じ、翻訳に取り組んだというお話をしてくださいました。
後半には、「アフリカ子どもの本プロジェクト」についてのお話もありました。
さくまさんの著書『エンザロ村のかまど』をきっかけに発足したこのプロジェクトでは、ケニアにドリームライブラリー(子ども図書館)を作り、その運営を支えたり、日本の子どもたちにアフリカの文化や子どもたちのことなどを紹介する活動を行っています。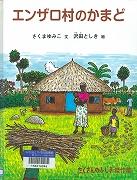
さくまゆみこ/文 沢田としき/絵
福音館書店
図書館の建物や、そこで本を読むこどもたちの様子などをスライドでご紹介いただきました。
青空の下、ライブラリアンによる読み聞かせにたくさんひとが集まっています。読んでいるのはスワヒリ語に翻訳された日本の絵本。
最後に、この活動をきっかけに日本での翻訳・出版に至った本をご紹介いただきました。
タンザニアのポップアート「ティンガティンガ」の手法で描かれた動物たちの絵が鮮やかな絵本『なかよしの水 タンザニアのおはなし』。前作『ごちそうの木』とともに、スイスやドイツなど数多くの国で翻訳されている絵本です。
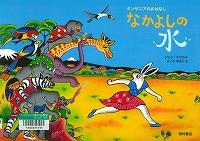
ジョン・キラカ/作 さくま ゆみこ/訳
西村書店
1時間と、とても短い時間ではありましたが、翻訳の難しさや大変さ、そしてなによりもその仕事の喜びや楽しさがたっぷりと聞けた講演会でした。
さくまさん、ありがとうございました!
第19期「本と出会う読書サロン」は、12月~2020年3月の毎月第3火曜日、午後7時から開催します。第19期各月のテーマは小説(12月「歴史」、1月「SF」、2月「ミステリー」、3月「恋愛」)。これらのテーマで、読書サロンのメンバーがどんな本を紹介するのか、気になる方は見学だけでもしてみませんか?
まずはメンバー登録をどうぞ。→詳細はコチラから
Posted at:16:00